筆者紹介
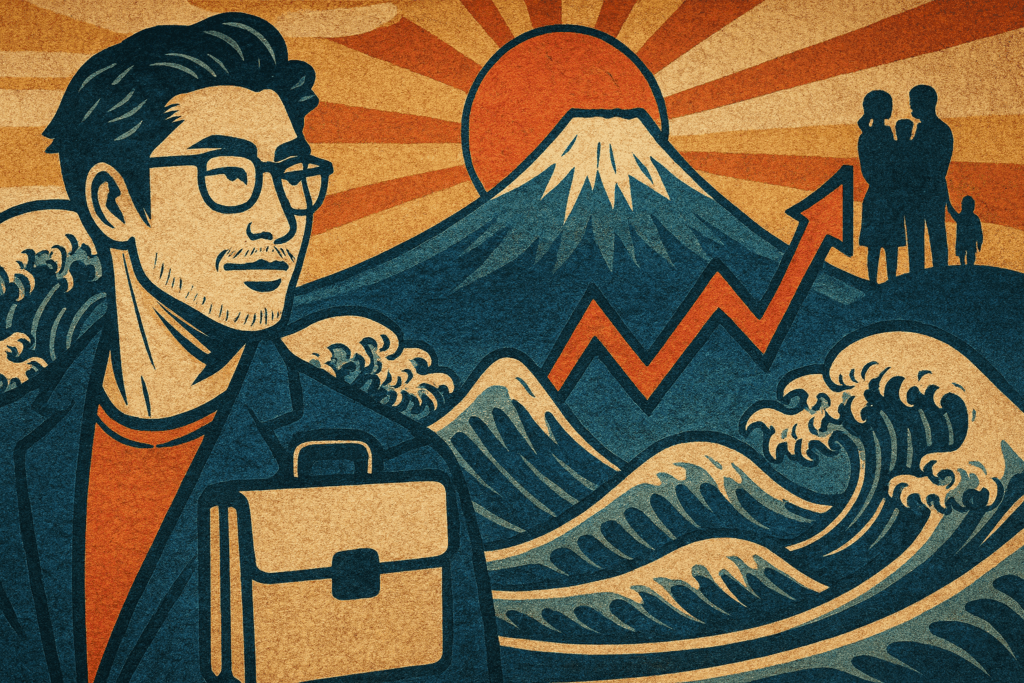
こんにちは。普段は企画職に携わりながら、効率的に働く工夫を研究している筆者です。今日は「仕事がだるい」と感じるときの乗り越え方について、脳科学と社会的背景を交えてお話しします。
To Do リストも作ったし、優先順位も決めたのに…ダルいんです
やるべきことは整理した。優先順位もばっちり決めた。
──なのに机に向かうと体が重く、手が止まってしまう。そんな経験はありませんか?
これは決してあなたの意志が弱いからではなく、脳が本来持っている仕組みや職場環境が影響しているのです。
なぜ「だるい」を感じるのか:科学的な根拠
「だるい=自分の意志が弱い」と思いがちですが、実は脳科学的に説明できる自然な反応です。
研究では、長時間の集中や判断の繰り返しで前頭前野に疲労物質が蓄積し、やる気や判断力が下がることが示されています。
さらに心理学で言う「意思決定疲労(Decision Fatigue)」では、決断を繰り返すほど自己コントロール力が消耗し、やがて「もう考えたくない=だるい」という感覚につながります。
意思決定は思った以上に脳に負担をかける
私たちは一日で約35,000回の意思決定をしていると推定されます。
食べ物に関する選択だけでも200回以上/日。
例えば──
- 朝の服選びで迷って疲れる
- 昼食を決めるのに時間がかかる
- ネットショッピングで比較に疲れ、結局買わない
こうした小さな判断の積み重ねが脳を消耗させるのです。
実際、イスラエルの研究では裁判官が仮釈放を認める割合が朝は約70%だったのに、午後には10%近くまで低下しました。判断を重ねるだけで、脳は「安全で簡単な選択」に傾いてしまうのです。
つまり「だるさ」とは、意思決定の過多から生じる脳の自然な反応なのです。
日本の職場文化が生む「だるさ」
ここに、日本特有の働き方が拍車をかけています。
- 長時間労働:休憩や睡眠が削られることで脳の回復が追いつかない
- 有給の取りにくさ:休息を取ること自体に罪悪感を抱きやすい
- 裁量の少なさ:自分で決められない業務が多いと、ストレスが積み重なり「気持ちが乗らない」状態になりやすい
こうした文化的背景は、「だるさ=甘え」と捉えがちな風土をつくり、休むことが難しくなる悪循環を招いています。
海外での取り組み:制度で疲労を防ぐ
一方、北欧などでは制度的に「だるさ」を減らす取り組みが進んでいます。
- 労働時間の短縮(1日6時間勤務の試験導入)
- フレキシブル勤務や在宅勤務の普及
- 休暇取得の奨励と義務化
これらの工夫は「休むこと=悪いこと」ではなく「パフォーマンスを保つために必要なこと」として文化的に定着しています。
だるさに効く3つの突破口
1. 最初の30秒だけやる
件名を書く、タイトルを打つなど、小さな着手を突破口に。
2. 型を決めて判断を減らす
フォーマットや手順を固定することで、意思決定の回数を削減。
3. 完璧を目指さず最後まで通す
粗くても仕上げることで「やった感」を得て、次につなげる。
まとめ:感情を押さえ込むのではなく、仕組みで軽くする
- 「だるさ」は脳の自然な反応であり、意思決定の過多が原因
- 日本の職場文化は「だるさ」を強めやすい環境をつくっている
- 海外では制度や文化で「疲労を予防する仕組み」が浸透している
- 小さな突破口と習慣化で、感情を味方にできる
だるい気持ちに勝つのではなく、だるさを前提にした働き方の工夫を取り入れることが、現実的で科学的な解決法です。

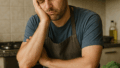

コメント