私は最近、**ファイナンシャル・プランナー3級(FP3級)**に合格しました。
正直に言うと、勉強を始めた頃は「専門用語が難しくて全然頭に入らない」「テキストを読んでも実生活にどう役立つのかイメージできない」と何度も壁にぶつかりました。きっと、同じように感じている方も多いのではないでしょうか。
そんな私でも、工夫を重ねるうちに少しずつ理解が深まり、「知識が生活に直結する実感」を得られるようになりました。だからこそ、この記事では――
私自身がつまずいたポイントや悩んだ用語を、かみ砕いてわかりやすくお伝えすること
を大切にしています。
FP3級をこれから目指す方にとっては「合格者が通った道のり」としての参考に、また「暮らしに役立つお金の基礎知識」としても読んでいただければ嬉しいです。
不動産の勉強をしていると、専門用語の中に「絶対高さ制限」という言葉が出てきませんか?
「高さ制限っていろいろあるけど、“絶対”って何が違うの?」
そんな疑問を抱いたままテキストを閉じてしまう方、多いと思います。
実はこの「絶対高さ制限」は、私たちの生活に直結している“静けさのルール”なんです。
この記事では、FP3級試験にもよく出るこのテーマを、身近な街の風景を思い浮かべながらわかりやすく解説していきます。
結論から言えば――
「低層住宅エリアは、絶対に高い建物を建てられない」。
この一言を理解できれば、試験も日常の街歩きもずっと楽しくなります。
絶対高さ制限とは?静かな住宅街を守るためのルール
そもそも「絶対高さ制限」ってなに?
結論から言うと、建物の高さに「これ以上はダメ」と上限を決めるルールのことです。
都市計画法や建築基準法に基づき、主に第一種・第二種低層住居専用地域に適用されます。
なぜそんな制限があるのか?
理由はとてもシンプルで、「静かで明るい住宅地の環境を守るため」。
たとえば、隣の家が突然4階建てを建てたら、日当たりや風通しが悪くなりますよね。
そうしたトラブルを防ぐために、「絶対にこの高さまで」と線を引いているのです。
ちなみに、上限は10mまたは12mのどちらか。
都市計画でエリアごとに指定されており、どちらも“低層らしさ”を保つ目安です。
次の一歩:
街を歩くとき、「このエリアは10mかな?12mかな?」と想像してみると勉強が楽しくなります。
第一種・第二種低層住居専用地域の違いをイメージでつかむ
第一種低層住居専用地域 ― 静けさと落ち着きの象徴
第一種は、いわば「住宅街の中の住宅街」。
本当に静かで落ち着いたエリアです。
基本的には住宅しか建てられませんが、例外的に小中学校や診療所など“生活に必要な施設”はOK。
ただし、コンビニやカフェのような店舗は原則NGです。
高さの制限はもちろん10mまたは12m。
つまり、どんなに頑張っても3階建てが限界。
それ以上の高さを求めるなら、別の用途地域で建てる必要があります。
この制限があるからこそ、朝の陽ざしがリビングに届き、子どもの声が静かに響く街並みが保たれるのです。
次の一歩:
家を建てるときは「どんな用途地域か」をまず調べてみましょう。建築会社任せにしないのが賢い選択です。
第二種低層住居専用地域 ― 生活の便利さを少しプラス
一方、第二種は「住宅を中心にしながら、ちょっと便利なお店もOK」という地域。
住宅街の中に、小さな美容室やパン屋さん、コンビニが点在しているイメージですね。
建てられるのは、床面積150㎡以下の店舗や事務所まで。
それ以上の規模になると、騒音や人の出入りが増えて住宅環境を壊す恐れがあるため制限されます。
それでも高さの上限は、やはり10mまたは12m。
つまり「便利さをプラスしても、空の広さは変えない」という考え方なんです。
次の一歩:
家探しや投資用不動産を選ぶとき、「静けさ優先なら第一種、利便性も欲しいなら第二種」と覚えておきましょう。
他の高さ制限との違い ― 「絶対」とつく理由
「高さ制限」と聞くと、ほかにも「斜線制限」がありますよね。
道路斜線、隣地斜線、北側斜線…。
これらは“建物の形を斜めに削る”ようにして日照を確保するルールです。
一方で、絶対高さ制限はもっとシンプル。
建物全体の高さに「天井」を設けるだけ。
どんなに工夫しても、その高さを超えてはいけません。
言うなれば、斜線制限が「形のルール」なら、絶対高さ制限は「存在の限界」。
だから“絶対”なんですね。
次の一歩:
FP試験では「斜線制限と絶対高さ制限の違い」を問われることが多いので、セットで覚えておきましょう。
まとめ
絶対高さ制限とは、
**「低層住宅地の空を広く保つための約束ごと」**です。
- 対象は第一種・第二種低層住居専用地域
- 高さの上限は10mまたは12m
- 目的は日照・通風・景観の保護
- 「絶対=超えられない」点が試験のキーワード
このルールのおかげで、静かで穏やかな住宅街が守られています。
街を歩くとき、空の高さを感じながら「これが絶対高さ制限か」と意識してみると、暮らしの見え方が変わるかもしれません。
次の一歩
- 【関連記事】用途地域の種類と特徴をわかりやすく解説
- 【学習用】FP3級「都市計画法」頻出問題まとめ
- 【実践編】マイホーム購入前に確認すべき3つの法規制
参考文献/出典
- 国土交通省「用途地域制度について」:https://www.mlit.go.jp
- 東京都都市整備局「建築基準法における高さ制限」
- FP協会公式テキスト『3級FP技能士学科試験対策』
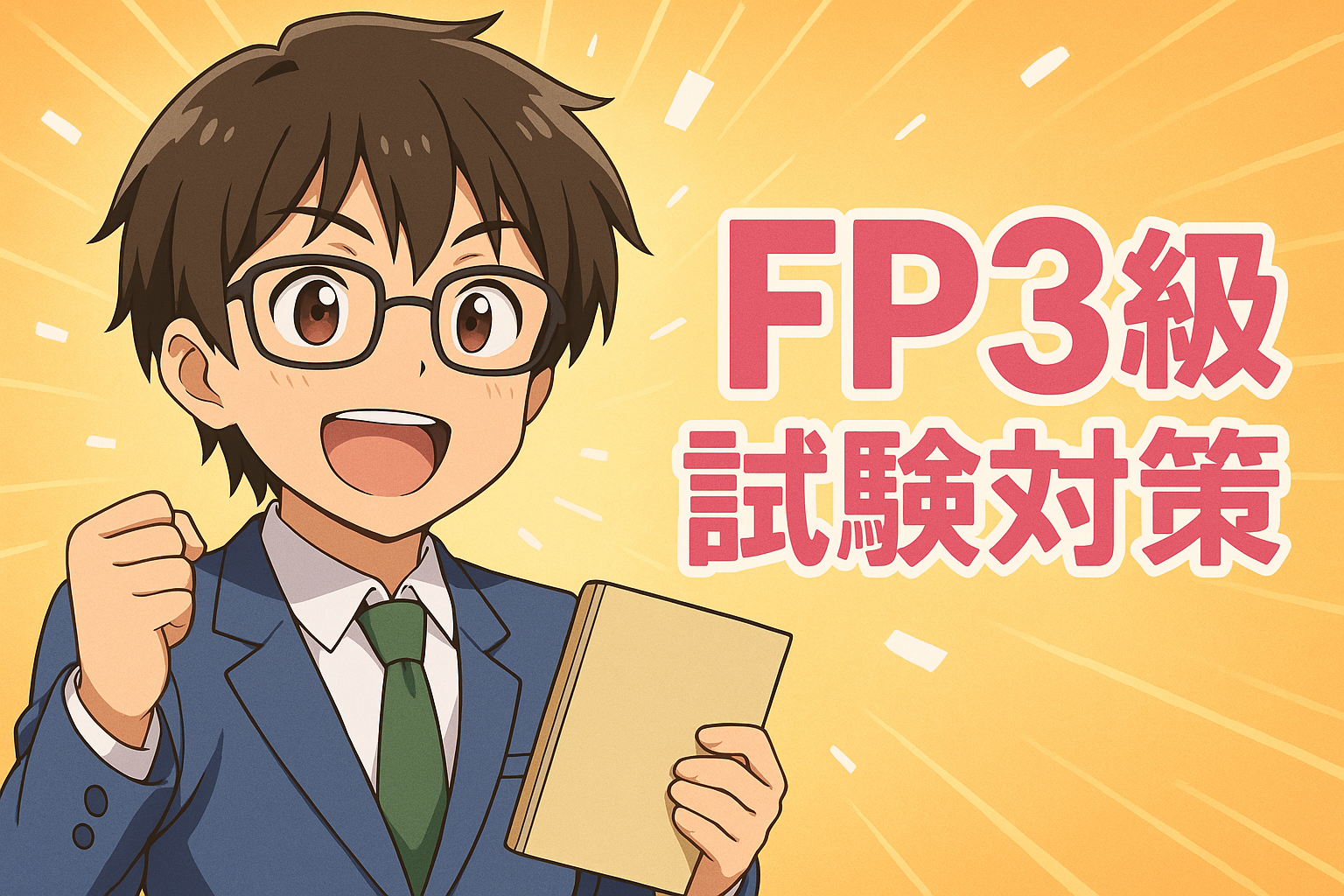


コメント