「アンガーマネジメント」とはよく言われますが、正直なところ──
「怒りをゼロにするなんて無理だろ!」と逆にイライラしてしまった経験はありませんか?
私も同じです。
「怒らない人間になろう」と思えば思うほど、かえって自分を追い詰めてしまう。
そんなとき、FPの勉強中にふと気づいたんです。
「怒りって、税金の計算に似ているのでは?」
この比喩を思いついた瞬間、怒りの扱い方がぐっと楽になりました。
怒り=所得
人は誰でも腹を立てます。
それを「なかったこと」にしてしまうと、後でまとめて“追徴課税”のように爆発してしまう。
だからまずは、正直に「私はいま10万円分くらい怒っている」と認めること。
感情を“所得”として可視化すると、不思議と客観視できるようになります。
控除=配慮
税金に控除があるように、怒りにも控除を適用できます。
- 妊娠中だから
- 新人だから
- 初めてだから
- 自分は大人だから
こうした事情を差し引くと、怒りの総額はぐっと減っていきます。
私自身も「彼はまだ入社1か月目だった」と気づいた瞬間、怒りの半分以上が消えていました。
残るもの=課税所得=社会に出す怒り
控除を差し引いて残ったもの──それが“課税所得”。
つまり、社会的に表現してよい怒りです。
例えばこう言えます。
- 「初めてなら仕方ないね。でも次はこうしてほしい」
- 「今の言い方には驚いたよ。落ち着いたら話そうか」
これは“節税後の怒り”。必要最小限に抑えられ、冷静に伝えられる形です。
専門家から見ても理にかなう
税理士の視点からすれば、この比喩は極めて妥当です。
税制は「公平な負担」を原則に、事情を控除で調整し、残った部分に課税します。
怒りも同じ。相手の事情を考慮したうえで残った感情だけを表すことが、公平で理にかなっています。
心理学の観点からも、この流れは「認知的再評価」という感情調整法そのものです。
一次感情としての怒りをまず認め、控除という再解釈を加えることで、二次感情としての表現を穏やかに調整する。
科学的にも実践的にも有効な方法なのです。
ただし、控除をすべて適用して怒りをゼロにする必要はありません。
税制に課税対象が残るように、感情も正当に伝えるべき場面があります。
抑圧しすぎることは健全ではなく、時には堂々と“課税”することも大切です。
FP学習が広げる「日常の読み替え」
この発想に至ったのは、FPを学んでいたからです。
税制の仕組みを知ることで、家計管理や投資だけでなく、日常の感情や人間関係まで“経済のレンズ”で読み替えられるようになりました。
FPの知識は単なるお金のツールではなく、人生を豊かにする思考の道具でもあるのです。
✅ 怒りの節税術チェックリスト
- 課税所得を確認する:怒りを正直に数値化する。
- 控除を適用する:相手の事情を差し引いて考える。
- 課税所得を再計算する:残った怒りは表現すべきか確認する。
- 適切に納税する:冷静な言葉や態度に変換して伝える。
- 還付を防ぐ:後悔しないよう、言いすぎを避ける。
まとめ
怒りをゼロにすることはできません。
しかし、税金の計算のように「正直に認め、控除を適用し、残った分だけを表現する」ことはできます。
これが私の提案する 「怒りの節税術」 です。
そして、この発想はFPを学んでいたからこそ生まれたもの。
学びが日常を読み替える力になり、人生をより豊かにしてくれるのです。

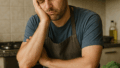

コメント