仕事から帰宅し、家族が寝ている中、ふと自分の内側に問いかけたくなる瞬間があります。
**「男性は育児に参加していない」**という言葉。
たしかに日常の風景を見れば、オムツ替えや寝かしつけを母親が担う家庭が多いのは事実でしょう。でも少し視点を変えると、私たちが頼りにしている育児理論や発達心理学の基盤は、男性研究者たちが築いてきたものなのです。
父親が築いた知の土台
育児の歴史をたどれば、こんな名前が並びます。
- フロイト(精神分析)
- ピアジェ(認知発達段階説)
- エリクソン(発達課題論)
- ボウルビィ(愛着理論)
どれも現代の育児書や子育て論に深く根を下ろしている理論です。
つまり父親は、家庭の外から「学問」という形で育児に関わり続けてきたのです。
データが語る現実
この「父親の科学的貢献」は、感覚だけの話ではありません。研究データもそれを裏付けています。
- 小児研究の論文15万件超を分析した調査では、最終著者(研究リーダー)の63%以上が男性でした。
- 家族医学分野の研究(2008–2018年)では、第一著者の65.5%、最終著者の71.9%が男性。
- 小児集中治療の臨床研究でも、著者全体のうち女性は38%にとどまっています。
著者全体の性別比は年々接近してきているものの、研究をリードする立場では依然として男性が多数派であることが明らかになっています。
それでも「育児していない」と言われる理由
では、なぜ父親は「育児に参加していない」と見なされるのでしょうか。
それは、現代における「育児参加」が、
- 夜泣きに付き合う
- ごはんを食べさせる
- 保育園に送り迎えする
- 公園で子どもと遊ぶ
といった家庭内での直接的な行為に限定されるからです。
研究でどれだけ成果を残しても、リビングや寝室で子どもと関わる姿が見えなければ、「不参加」と評価されやすいのです。
ギャップが示すもの
この「科学的貢献」と「家庭内貢献」のギャップは、父親を責めるためのものではありません。
むしろ、時代が父親に求める姿を映す鏡のようなものです。
- かつての父親:知をつくり、体系化する人
- 現代の父親:子どもと共に育つ人
社会の変化とともに、父親像も「提供者」から「伴走者」へと移行しているのです。
結び
父親はこれまで「研究と理論」という形で育児に関わってきました。
そしてこれからは「家庭での時間」を通じて関わる時代に入っています。
どちらの姿も育児参加であり、どちらの貢献も価値あるもの。
大切なのは、母と父、それぞれの役割を尊重し合うことではないでしょうか。
あなたにとって「父親の育児参加」とはどんな姿でしょう。
静かな夜に、少しだけ考えてみていただけたら幸いです。
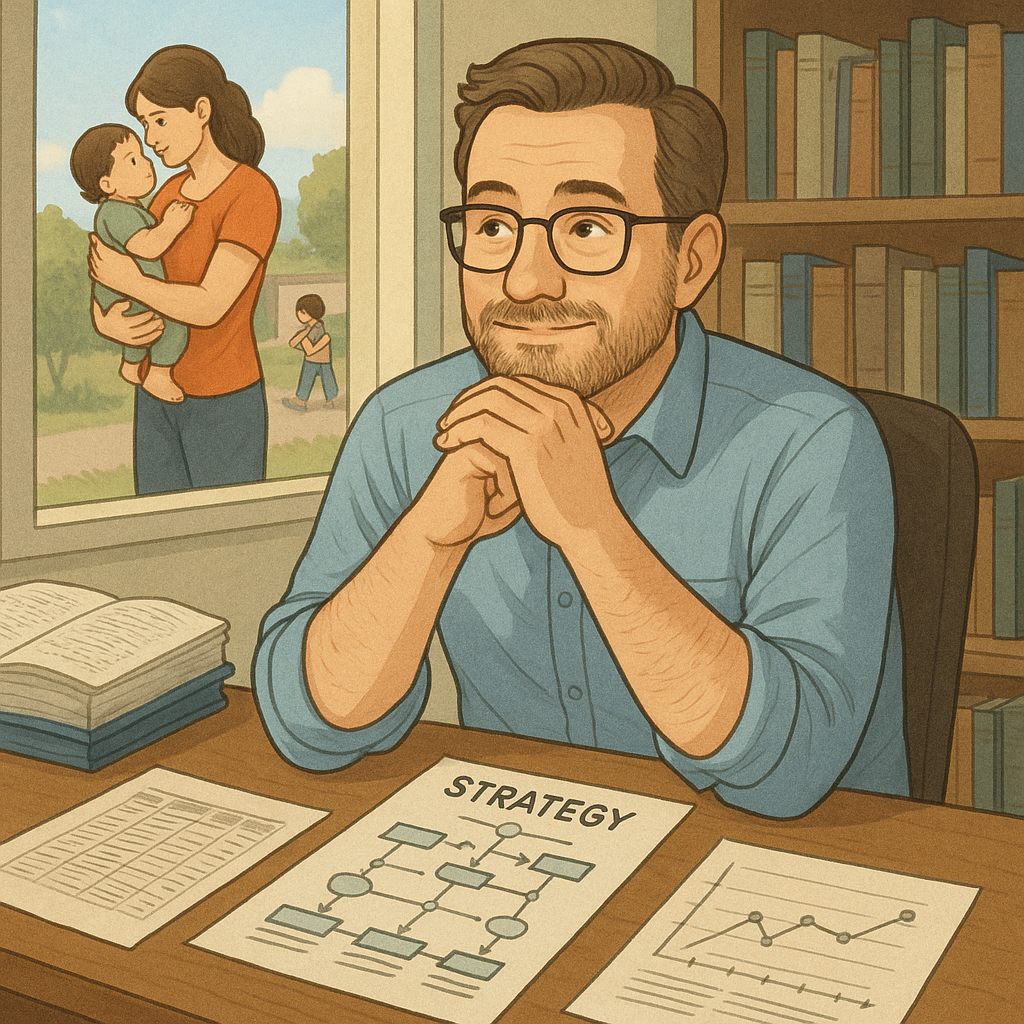
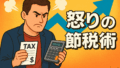

コメント