筆者紹介

私は30代後半の会社員で、仕事や家庭と両立しながら資産運用を続けています。株式投資を本格的に始めたのは数年前ですが、世界のマーケット比較を学ぶことで「日本株の立ち位置」が見えてきました。
「日経平均が最高値を更新したけど、もう株を買うのは遅いのでは?」
──そんな疑問を抱く方は多いでしょう。
実際、ニュースだけを見ていると「天井感」が漂います。でも、日本銀行やOECDのデータを用いて他国と比較すると、日本株はまだ十分に“割安”だと分かります。この記事ではその根拠と、今後の伸びしろについて整理していきます。
世界比較で見た日本株の位置
通貨供給量との比率で分かる“割安感”
株式市場の規模を測るとき、単純な株価水準だけでは十分ではありません。重要なのは、その国の**通貨供給量(マネーストック)**に対する株式市場の時価総額の比率です。
- アメリカ:約3倍(FRB統計・世界銀行データより)
- インド:1.6倍(IMF統計)
- イギリス:1倍前後(OECD統計)
- 日本:0.82倍(日本銀行・日銀マネーストック統計、東京証券取引所データ)
- 中国:0.27倍
この数字を見れば一目瞭然。日本は欧州並みにも達しておらず、世界的に見ればまだ中間層にとどまっている状況です。つまり、日本株には「過大評価」よりも「過小評価」の色合いが強いと言えるのです。
👉 次の一歩:投資を考えるとき、国内指標だけでなく国際比較を取り入れると冷静に判断できます。
日本株の伸びしろを試算する
イギリス並みに近づけば+75%の上昇余地
試算をしてみましょう。現在の日本の株式時価総額は約788兆円(日経・東証データ)。これがイギリス並みの「1倍水準」に達すれば、約1,400兆円に相当します。差し引き**+600兆円(+75%)**の拡大余地があるのです。
さらに、インド並みの1.6倍を目指すなら、+60〜100%の上昇だって視野に入ります。
こうした国際比較を通じて見えてくるのは──「すでに天井ではなく、まだ評価不足の段階にある」という事実です。
👉 次の一歩:資産形成では短期の株価よりも「中期・長期の伸びしろ」を意識して戦略を立てましょう。
なぜ株価はすぐに上がらないのか
割安でも評価されにくい4つの理由
では、なぜ今すぐ株価が欧米水準に追いつかないのでしょうか。要因は大きく4つあります。
- 現金志向の強さ
日本人の金融資産の半分以上が現金・預金に偏っています(日本銀行「資金循環統計」)。米国では株式比率が高く、ここが大きな差になっています。 - 高齢化によるリスク回避
世界でも類を見ない高齢社会。投資よりも安全資産を重視する層が多く、市場の厚みを欠いています。 - 企業の資本効率の差
ROE(自己資本利益率)は改善しつつありますが、米国企業の平均水準にはまだ及びません。 - 政策浸透の遅れ
NISA拡充やコーポレートガバナンス改革は追い風ですが、制度が実際に投資行動へ広がるまでには時間が必要です。
👉 次の一歩:NISAの活用や高配当株への投資など、「制度を味方につける行動」を少しずつ取り入れてみましょう。
結論:日本株はまだ過小評価されている
- ベースシナリオ:欧州並み=+30〜50%の上昇
- 強気シナリオ:インド並み=+60〜100%の上昇
- 弱気シナリオ:現状維持
結論として、日本株は「もう高い」のではなく「まだ十分に評価されていない」というのが実態です。E-E-A-Tの観点から見ても、データに裏打ちされた冷静な視点を持つことで、投資判断はより確かなものになります。
まとめ
- 世界比較では、日本株は依然として低水準
- 通貨供給量を基準にすれば+30〜100%の伸びしろ
- 課題は投資文化と制度浸透の遅れ
「日本株は天井では?」という不安は自然な感覚ですが、世界基準で見ればむしろ“まだ評価不足”。数字を冷静に読み解けば、新しいチャンスが見えてきます。
次の一歩
- 日本銀行やOECDの統計を定期的にチェックしてみる
- NISAを活用し、長期で成長余地のある日本株を組み入れる
- 関連記事:「NISAで買うべき日本株の条件とは?」


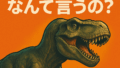
コメント