子育てをしていると、こんなシーンに出会うことはありませんか?
夕方、夕飯前。子どもが夢中で積み木を積み上げ、ようやく高く積めたと思ったら、バランスを崩して崩れてしまう。次の瞬間、子どもは泣きながら、残っていた積み木まで全部壊してしまう──。
大人にとっては「せっかく作ったのにもったいない」と映る行動ですが、発達心理学をひもとくと、子どもには子どもなりの“ルール”があることが見えてきます。
1. ピアジェの「前操作期」──感情と対象の同一視
発達心理学者ジャン・ピアジェ(Piaget, 1952)は、2〜6歳を「前操作期」と呼びました。
この時期の子どもは、論理的思考よりも直感や自己中心性に支配されます。
つまり「悔しい気持ち」と「目の前の積み木」を区別できず、作品=自分の感情そのものとして扱ってしまうのです。壊すことは「気持ちを外に出す」行為でもあるのです。
2. エリクソンの発達段階──「自律性 vs 恥・疑惑」
エリク・エリクソン(Erikson, 1950)は、2歳前後を「自律性 vs 恥・疑惑」の発達課題に位置づけました。
子どもは「自分でやりたい」という欲求が強まる一方で、うまくいかないと「恥ずかしい」と感じます。
例えば、パズルが最後に入らず、悔しさのあまり全体を壊してしまうのは、**「失敗した自分を直視するより、全部リセットした方が心が楽」**だからなのです。
3. Amselの「フラストレーション理論」──リセット欲求
心理学者Amsel(1958)は、期待が裏切られたとき、幼児は強いフラストレーションを示すと報告しました。
「思い通りにいかない」ことは、2歳児にとって耐えがたい体験です。
だから積み木が崩れた瞬間に「全部なかったことにしたい」という気持ちが爆発し、作品を壊す=リセット行動として現れるのです。
4. ヴィゴツキーの視点──言葉より行動で表す
レフ・ヴィゴツキー(Vygotsky, 1934)は、幼児期は感情を言葉に変換する力が未発達であり、行動を通じて表現すると述べました。
「悔しい!」と伝えられない代わりに、積み木やケーキを壊す行動で気持ちを表すのです。
大人から見ると“破壊行動”でも、子どもにとっては“感情の言語化”の代わりなのです。
親にできるサポート
発達心理学の視点を踏まえると、子どもが爆発したときに大人ができることは次のようになります。
- 感情を代弁する:「せっかく作ったのに壊れちゃって悔しかったね」
- リセットの場を用意する:「もう一回やってみようか」と再挑戦のきっかけを与える
- 安全な発散手段を示す:クッションを叩く、紙を破くなどで気持ちを出せるようにする
年齢別:親が掛けてあげたい言葉
2歳
「壊れちゃったね。でも大丈夫。また一緒に作ろうね」
→ シンプルな言葉で安心感を与える
3歳
「悔しかったんだね。でも壊れても、またできるよ」
→ 感情を認めつつ「やり直せる」ことを伝える
4歳
「すごく頑張ってたの見てたよ。壊れたけど、次はもっと上手にできるかもね」
→ 努力を認め、未来への期待を示す
5歳
「壊れちゃったときは悔しいよね。でも壊れるのも大事な経験なんだ。次はどうしたらうまくいくと思う?」
→ 感情を共感しつつ、振り返りと考える力を促す
おわりに
「作品を壊す」という行動は、大人にとっては理解しがたいものです。
しかし発達心理学的には、それは 感情表現・自己防衛・リセット欲求・未発達な言語能力の代替 といった複数の要素が重なった自然な行動。
そして、その瞬間に親がどんな言葉を掛けるかが、子どもの心に安心と自信を積み重ねていきます。
“破壊”は無駄ではなく、次の成長につながるプロセスなのです。

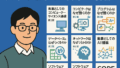

コメント