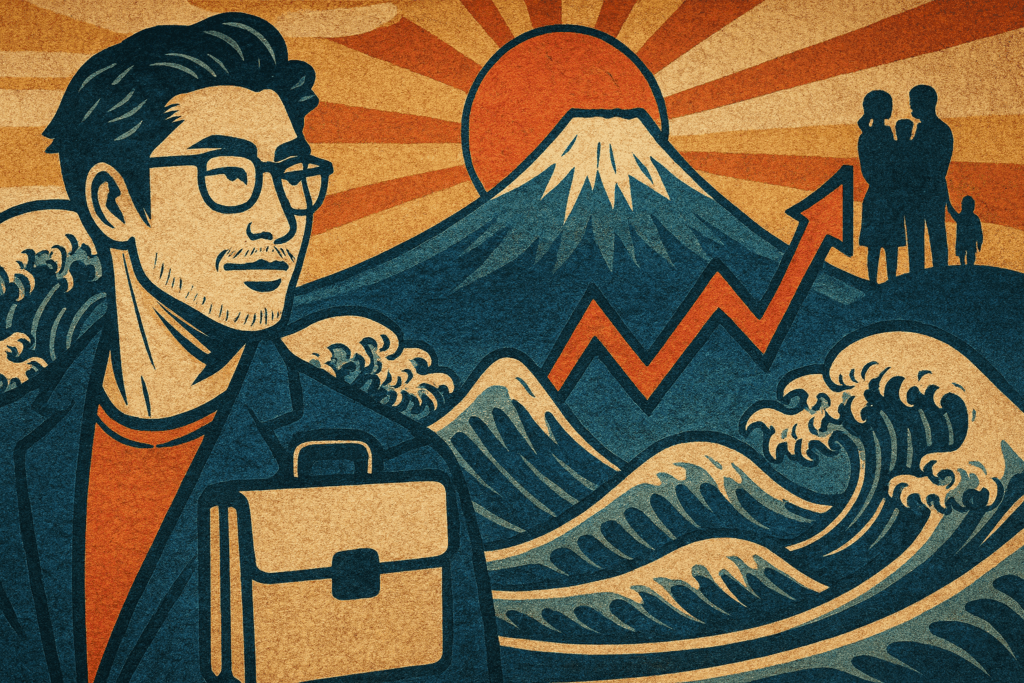
筆者紹介
金融・家計改善の編集・コーチングを行い、共働き家庭の資産設計を複数サポートしてきたサラリーマンです。Notionで整理した手法を使い、読みやすく実行しやすい設計図をお届けします。
質問
「共働き家庭は、どうやって無理なく貯めて、将来の不安に備べばいいの?」
共働きは収入が増える一方で、家事育児負担・税制・教育費などでお金の出口も増えます。**結論:家計は『可視化→役割分担→自動化(積立)→制度最適化』の順で整えれば、無理なく資産を作れます。**この記事は、具体的な手順と即できるチェックリストを示します。
まずは現状把握と目標設定(共働き家庭の資産設計)
結論 — 目標は「共通の数値」で合わせる
結論:**短期(1年)→中期(3–7年)→長期(10年以上)**の3軸で目標を数値化する。
理由(Why):共働きでは価値観や優先順位がズレやすく、数値が揃うと意思決定が速くなるため。
具体例:住宅購入(頭金◯◯万円)、教育費(子1人あたりの教育費目標)、老後(毎月必要額)。
How to(手順):
- 月収(手取り)を可視化:夫/妻それぞれの手取りを表にする。
- 固定費・変動費を分ける(3ヶ月分の実績を取得)。
- 目標を3軸で設定し、それぞれに必要な総額を算出する(教育費は学資保険+投資を併用)。
まとめ+次の一歩:まずは今月の収入と3ヶ月分の出費をNotionや家計アプリに入力する。
次の一歩:今月の「手取り合計」と「固定費合計」を記録してみましょう。
リスク管理(保険・緊急資金)の設計
結論 — 緊急資金は生活費3〜6ヶ月分、保障は家族単位で最適化
結論:非常時に生活を維持できる現金(流動資産)を最優先に確保し、重複する保険は整理する。
理由(Why):ショック時に資産を切り崩さないことで長期的な投資戦略が破綻しにくくなる。OECDデータでも家計の貯蓄行動は景気や不確実性に影響を受けることが示されています。OECD
具体例:共働きで片方が休職した場合、ローン返済+生活費を賄えるだけの現金。子の急病に備えた短期的医療費。
How to(手順):
- 緊急資金:生活費×3〜6ヶ月を普通預金やすぐ引き出せる口座で確保。
- 保険の棚卸し:生命保険・医療保険は家族全体で重複がないか見直す(会社の団体保険も確認)。
- 非常時の役割分担:誰が家事・育児を担うか、収入減の場合の優先支出を決める。
まとめ+次の一歩:まずは家族で「優先支出リスト」を作成し、緊急資金の不足額を確認する。
次の一歩:生活費の3ヶ月分を即時振替口座へ移してみましょう。
投資・積立の基本設計(税優遇を活かす)
結論 — まずは税優遇制度(iDeCo/NISA等)→ つみたて投資の自動化
結論:共働きは税制・制度の使い分けで効率が変わる。優先順位は「緊急資金→税優遇での積立→老後投資」。
理由(Why):制度を活かすと同じリスクで手取りが増えるため。海外や実務者のガイドでも、制度活用と自動積立が有効とされます。フィデリティ
具体例:つみたてNISAを満額、iDeCoで拠出(勤務先のマッチ拠出があるなら優先)/子ども教育費はジュニアNISAや学資と併用。
How to(手順):
- それぞれの制度枠を確認(自分・配偶者別)。
- 生活防衛資金を確保した上で、毎月自動で引き落とされる設定にする(「先取り貯蓄」)。
- リスク許容度に応じて、インデックス中心の分散ポートフォリオ(例:先進国株+国内債券等)を設計。
まとめ+次の一歩:まずは銀行口座から「月額自動積立」設定を行い、NISA枠の検討を始める。
次の一歩:つみたてNISA口座の開設(または現状の投信設定をCSVで確認)を行いましょう。
税制・社会保障・家計ルールの最適化(共働きならでは)
結論 — 税制上の選択(扶養・社会保険)と家計ルールを合わせる
結論:扶養や社会保険の選び方で手取りや保障が変わるので、家族全体で最も効率的な組合せを検討する。
理由(Why):片方が手取り増を優先すると、別の損(扶養の喪失で税負担増)が起きる場合がある。
具体例:配偶者控除のライン、健康保険の被扶養認定、育休制度の賢い使い方。
How to(手順):
- 年収ラインごとに手取りシミュレーションをして「実効税率」を確認。
- 会社の社会保険制度や育休給付を確認して、どちらが残業で稼ぐべきかを判断。
- 毎年見直すルールを家族会議で決める(年1回)。
まとめ+次の一歩:今年の年収見込みで「扶養」「iDeCo利用可否」などを試算してみる。
次の一歩:給与明細を1枚用意し、年収ベースで手取りと控除をシミュレーションしてみましょう。
家族の役割分担とコミュニケーション設計(心理的安全の確保)
結論 — 役割を可視化すると投資・家計の“継続”が続く
結論:ルールを決め、**月1回の家計ミーティング(15–30分)**を習慣化するだけで、家計の齟齬が減る。
理由(Why):共働きは情報非対称になりやすく、定期確認がズレを早期に直す。
具体例:毎月の数字チェック、年1回の目標見直し、子どもの教育方針確認。
How to(手順):
- 月次テンプレ(収入/固定費/積立額/今月の優先課題)を作る。
- 担当を決める(支出入力担当、制度チェック担当など)。
- 小さな成功(積立が続いたら月次で「見える化」)を褒め合う。
まとめ+次の一歩:テンプレを1つ作り、次回の家計ミーティングで使ってみる。
次の一歩:次の週末に15分、家計の現状(収入・固定費)を共有する場を設定しましょう。
参考
- 家計の貯蓄・貯蓄行動に関する国際データ(OECDの貯蓄率など)を参考にしました。OECD
- 家族間の金銭コミュニケーションや制度最適化についての実務的ガイド(Fidelityなど)を参照しました。フィデリティ
また、記事の構成やSEO方針はご指定のNotion資料を参照して作成しています(文章術/プロンプト)。
まとめ
共働き家庭の資産設計は「見える化 → 最低限の安全網(緊急資金/保険)→ 税優遇の自動積立 → 家族での定期確認」の順で進めると、無理なく継続できます。小さな自動化(毎月の積立)と年1回のルール見直しが継続の鍵です。
次の一歩(気軽に試せる提案)
- 家計の「手取り合計」と「固定費合計」を今月分でメモする(所要15分)。
- 緊急資金が不足している場合は「まず生活費の1ヶ月分」を移す(即実行)。
- つみたてNISAかiDeCoの口座開設を検討し、月◯円の自動積立を設定する(小額からでOK)。

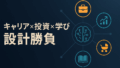

コメント